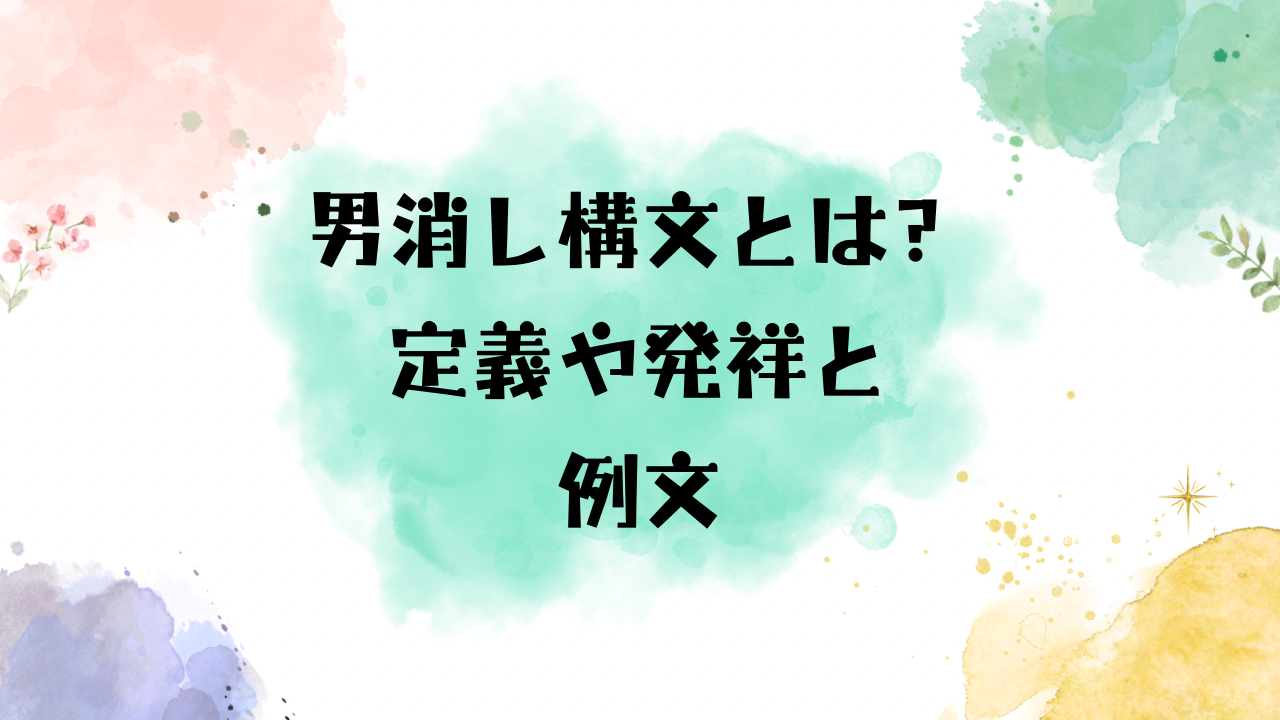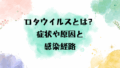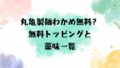近年、SNSやネットメディアなどで「男消し構文(おとこけしこうぶん)」という言葉を目にすることが増えてきました。この言葉は、文章表現の中で男性という性別や存在を意図的、または無意識に“消してしまう”文体を指します。一見するとただの言い回しに見えるかもしれませんが、その背後には社会的・文化的なジェンダー観や言葉の使い方に対する感覚の違いが潜んでいます。
本記事では、男消し構文の定義やその発祥、具体的な例文を紹介するとともに、SNS文脈だけでなく、報道記事などで“男性”という主体が消されているケースも含めて考察します。表現の中にある「見えない意図」に気づくことで、より言葉に対して敏感になれるはずです。
⸻
男消し構文とは?定義と発祥
定義
「男消し構文」とは、本来“男性”が主語であるはずの行為や文脈において、主語や性別を省略したり、あえて女性を主語に置き換えることで、男性の存在を見えにくくする構文のことを指します。
この言葉は、主にSNSユーザーによって造語され、特にフェミニズムにまつわる議論の中で用いられるようになりました。
例:
• 男性が女性に対して不適切な行動をとった場合:
• 元の構文:「男性に痴漢されました」
• 男消し構文:「痴漢されました」
→ 主語を省略し、“誰が”という加害者の性別を消している。
• 男性が加害者である事件の報道:
• 元の構文:「男性が女子高生に声をかけてつきまとった」
• 男消し構文:「女子高生が声をかけられ、つきまとわれた」
→ 受け手主体の受け身構文となり、加害者がぼかされる。
発祥
明確な発祥元は定かではありませんが、2020年代初頭のTwitter(現X)界隈で自然発生的に広まった表現です。フェミニズム的な文脈で「男性性を強調する表現が不快」とする意見の中から、意図的に性別表記を避ける傾向が現れ、その様式を皮肉を込めて「男消し構文」と呼ぶようになりました。
⸻
SNSに見る典型的な「男消し構文」の例
恋愛系投稿での男性の“消去”
恋愛系のあるある投稿やエピソードにおいて、男性の存在が意図的に消されている例がしばしば見られます。
例1:
• 普通の表現:「彼氏が私の誕生日を忘れていました」
• 男消し構文:「誕生日を忘れられました」
→「誰に?」という問いが生まれるが、主語は出てこない。読者に想像を委ねるようなぼかし方がされている。
例2:
• 普通の表現:「元彼に浮気されました」
• 男消し構文:「浮気されて、信じられなくなった」
→ 加害者側の性別や関係性が明示されず、“被害感”だけが強調される。
育児・家庭内投稿での父親の不在
家事・育児に関する投稿でも、父親の関与が曖昧化されるケースがあります。
例3:
• 「夜泣き対応して寝不足なのに、誰も助けてくれない」
→ 家庭内に“誰か”がいるはずだが、その存在は明示されない。
例4:
• 「保育園の準備も全部こっちがやってる」
→ “こっち”とは誰なのか。逆に“あっち”はどこにいるのか?
このような表現は、母親側の苦労を際立たせる一方で、父親の不在を“当たり前”として書き手も読み手もスルーしてしまう構図になっています。
⸻
報道記事に見る「加害者男性の存在のぼかし」
ニュースや報道においても、“男性”という属性があえて明記されない事例があります。これも広義の男消し構文として見ることができます。
犯罪報道における「受け身構文」
例1:痴漢事件
• 明確な表現:「40代男性が満員電車で女子高生に痴漢をした」
• 男消し構文:「女子高生が満員電車内で痴漢被害にあった」
→ 加害者の性別が省略され、あたかも“自然災害”のようなニュアンスに。
例2:性暴力事件
• 明確な表現:「会社員の男性が同僚女性にわいせつ行為」
• 男消し構文:「同僚女性が職場でわいせつ被害に遭った」
→ 行為の主体が誰かをぼかすことで、事件の印象が弱まる。
類例:ストーカー・つきまとい
• 「帰宅途中の女性がつきまとい被害に遭いました」
→ 加害者は存在するはずだが、性別・年齢などの属性情報は伏せられるケースが多い。
これは、「加害者=男性」という前提が当たり前すぎて書く必要がないと判断されている可能性もありますが、それにしても被害の文脈だけが残り、加害者の責任が曖昧になる傾向があります。
⸻
なぜ「男消し構文」が使われるのか?
1. 被害者の感情に寄り添うため
感情的なショックを共有する際、相手の存在を明示することがトラウマを呼び起こす場合もあり、あえて“主語を消す”ことで心理的距離を保っていることもあります。
2. 不特定多数に配慮する中立性
企業や報道機関は、ジェンダー表現に関して非常に慎重になっています。「男性」という表現がステレオタイプを助長するという批判を避けるため、性別表記を避けることも。
3. 共感と拡散を得やすい文章構成
SNSでは、「共感されるかどうか」が投稿のバズりに大きく影響します。あえて曖昧にした表現は、読者自身の体験に重ねやすく、拡散力が高まるという一面もあります。
⸻
「男消し構文」の功罪
メリット
• 被害者の尊厳やプライバシーを守ることができる
• 表現が柔らかくなり、読む側のストレスが軽減される
• 投稿の普遍性・共感性が高まる
デメリット
• 主語を消すことで、加害者の責任や構造的問題が見えにくくなる
• 曖昧な表現が事実認識をぼかす可能性がある
• 男性の存在や行動が常に“負の文脈”で処理されるという不満の温床にもなる
⸻
結局、「男消し構文」は悪いことなのか?
一概に善悪で語ることはできません。「男消し構文」が生まれる背景には、言葉の受け手や文脈、感情的な安全性の確保といった複雑な要素が絡んでいます。ただし、情報を発信する側・受け取る側のどちらもが、“何が語られていないか”にも意識的になることが、フェアで誠実なコミュニケーションには必要です。
⸻
まとめ
「男消し構文」は、SNSに限らず日常的な言語表現や報道の中にも多く見られます。
意図的か、無意識か。
被害者を守るためか、責任を曖昧にするためか。
言葉の背後にある意図やバイアスに気づくことで、表現を見る目は格段に鋭くなります。
「見えない主語」に気づけたとき、私たちは初めて、より深く社会の構造と向き合うことができるのかもしれません。