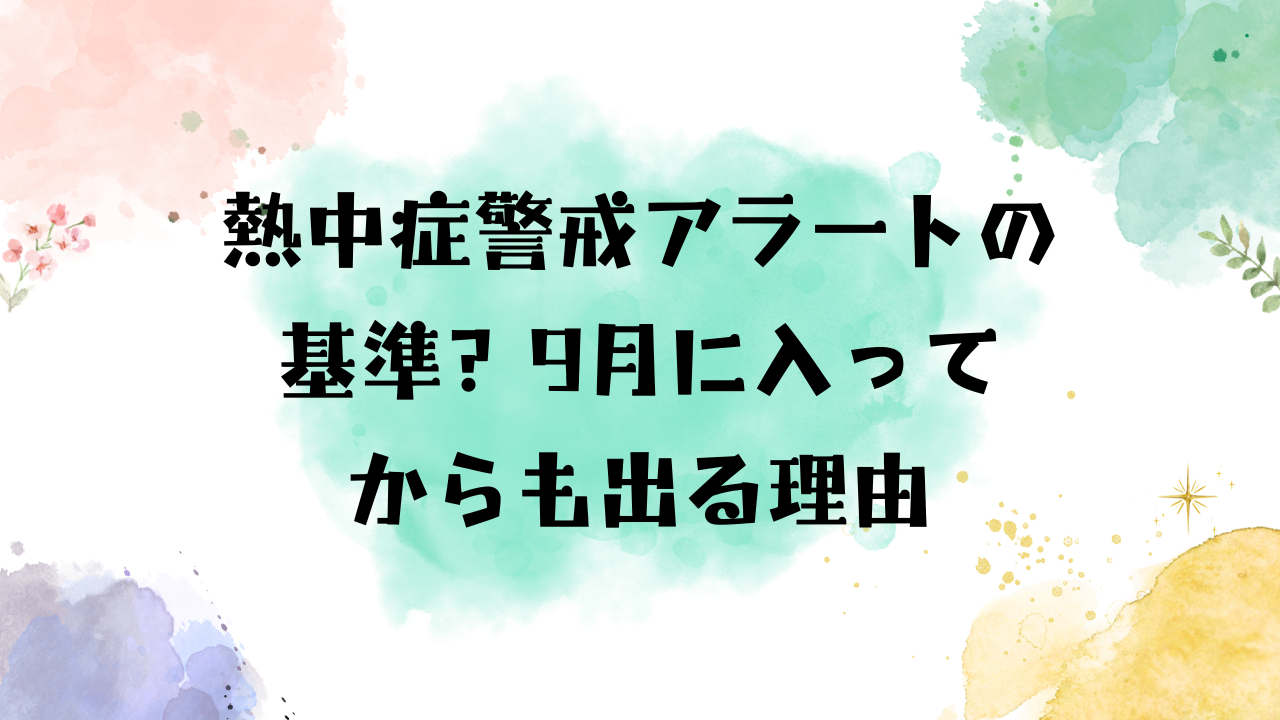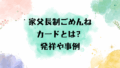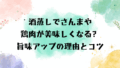真夏のピークを過ぎ、暦は秋に近づいても、熱中症のリスクが完全になくなるわけではありません。実際、9月に入ってからでも気温・湿度・日射などの条件が重なり、「熱中症警戒アラート」が発表されることがあります。では、熱中症警戒アラートとは具体的にどういう基準で、いつ、どのようなタイミングで発されるのか。さらに、なぜ9月でもアラートが出ることがあるのか、その背景や注意点を過去のデータを交えて整理してみましょう。
熱中症警戒アラートとは何か:制度の概要と目的
制度の導入経緯
- 日本ではここ数年、猛暑や熱中症による健康被害が増加しており、その予防対策の強化が求められていました。従来は「高温注意情報」などの基準で猛暑日の予報をもとに注意喚起をしてきましたが、気温だけでは熱中症リスクを十分に捉えられないとの指摘があったためです。 気象庁+3一般財団法人消防防災科学センター |+3ツギノジダイ+3
- 2020年以降、気象庁と環境省が連携し、「暑さ指数(WBGT:Wet-Bulb Globe Temperature)※ 気温・湿度・日射などを総合した指標」を活用する方式へ移行しました。これにより、気温だけでなく湿度や日射量などの要素を加味し、より実態に即した発表が可能となっています。 tenki.jp+2株式会社ノジマ+2
アラートの種類と目的
現在、主に以下2種類の警戒情報があります:
- 熱中症警戒アラート
熱中症の危険性が「極めて高くなると予測される暑熱環境」の際に、暑さへの「気づき」を促し、国民に予防行動を働きかけるもの。 WBGT公式サイト+2気象庁+2 - 熱中症特別警戒アラート(または熱中症特別警戒情報)
より一段階厳しい条件で、過去に例のないほどの危険な暑さ、あるいは重大な健康被害が生じる可能性が高いと予測されるときに発表されるもの。学校・イベント等の責任者や管理者への対応促進が強調されます。 ツギノジダイ+2気象庁+2
発表基準:暑さ指数(WBGT)を中心に
暑さ指数(WBGT)とは何か
暑さ指数(WBGT)は、以下のような要素を組み込んだ指標です:
- 気温
- 湿度
- 日射/輻射熱
- 日影や風の有無など(熱環境全体) WBGT公式サイト+2tenki.jp+2
これにより、「気温はそんなに高くないが湿度が非常に高い」「日差しが強く屋外にいるとき」など、体感・実際の熱ストレスが高まる状況を捉えることができます。
熱中症警戒アラートの具体的基準
- 発表対象地域:全国を58の府県予報区等に分け、1地域ごとに判断。 気象庁+1
- 発表条件:対象地域の中の少なくとも一つの暑さ指数(WBGT)算出地点で、「日最高暑さ指数を33以上と予測」される場合に「熱中症警戒アラート」が発表されます。 気象庁+2気象庁+2
- 発表のタイミング:通常、前日17時頃および当日午前5時頃の2回、最新の予測値をもとに発表されます。 気象庁+2気象庁+2
- 運用期間:毎年、4月第4水曜日の17時から10月第4水曜日の5時までがアラート情報の提供対象期間となっています。期間外でも暑さ指数のデータは収集されていますが、アラートとしての発表は休止中となります。 気象庁+1
熱中症特別警戒アラートの基準
- 基本的には、対象地域内のすべての暑さ指数情報提供地点において、翌日の**日最高暑さ指数(WBGT)**が35以上と予測される場合に発表される。これは「過去に例のない広域的な危険な暑さ」とみなされる条件。 ツギノジダイ+2気象庁+2
- また、発令時には通常のアラート以上に、外出制限やイベント・作業中止なども含めた行動制限を検討するよう呼びかけられることがあります。 ツギノジダイ+1
過去の発表状況:どれくらい出ているか、いつがピークか
アラートの発表回数の推移
- 気象庁・環境省の統計によれば、令和3年(2021年)からアラート制度が本格稼働し、年々発表回数は増加傾向にあります。 気象庁+1
- 最新では令和6年度以降(制度の運用開始から継続)でも、発表回数が増えており、猛暑傾向が“常態化”しつつあることを示しています。 気象庁+1
季節・月別の傾向
- 発表期間が4月下旬~10月下旬とされており、5~9月が最も頻度が高い。特に7月~8月の真夏期がピークです。 気象庁+2WBGT公式サイト+2
- ただし、9月にもアラートが出ることがあります。これは真夏のような高温+湿度条件+残暑+昼夜の温度差などが重なるためで、過去の発表履歴にも9月中旬~下旬での発出例が複数あります。 (環境省「熱中症警戒アラート等 発表状況と発表履歴」などで確認可能) WBGT公式サイト+1
なぜ9月でも熱中症警戒アラートが出るのか
9月に入ると「もう夏も終わりか」と思いがちですが、実際には以下のような理由で熱中症警戒アラートが発表されることがあります。
残暑・気温の高止まり
- 太平洋高気圧などの影響で、真夏と同様に暑さが続く日が多くなります。昼間の気温が高いうえ、夜間の気温があまり下がらず、熱がこもりやすい状況になることがあります。 Daigasコラム/大阪ガス
- 気象庁の予報でも、9月・10月の気温が「平年より高い」見通しとなることが度々あり、これが残暑として体感されます。 Daigasコラム/大阪ガス
湿度・日射・風などの複合要素
- 湿度が高いと、発汗しても汗が蒸発しにくく、体温調節が難しくなります。夜になっても湿度が下がらないケースもあり、熱疲労が蓄積します。
- 日射(直射日光の強さ)や輻射熱も体感温度を上げます。晴れて日差しが強い日は、影の少ない場所では特に危険です。
- 風が弱かったり、夜間も蒸し暑さが残っていたりすると、熱が抜けにくいため身体への負荷が続くことになります。
人の体の慣れ・対策意識の低下
- 夏の終わりに近づくと、暑さや日差しに対する意識が緩む傾向があります。「まだ9月だから大丈夫」「日陰なら平気」と思って行動が軽くなることがあります。
- また夏の疲労が残っていたり、睡眠が不十分であったり、水分補給を怠ることも多くなります。これらが重なって“体の中に熱がたまりやすい”状態を招きます。
昼夜の気温差・夜の暑さ
- 日中は気温が下がっても、夜に気温があまり下がらないと熱が体内にこもることがあります。特に夜間の高湿度環境だと寝苦しく、十分に冷却されないことがあります。これは“熱中症の予防”において甘く見られがちな部分です。
- 屋内でもエアコンを切るなど対策を怠ると、寝ている間に体温・深部体温が上がってしまうことがあります。
気象パターンの変動と異常気象
- 地球温暖化の影響により、かつてよりも気温・湿度が高止まりする日が増えています。夏から秋への過渡期においても“真夏並み”または“猛暑に近い”条件が現れやすくなってきているというデータがあります。 エバーグリーン・マーケティング
- また台風の後の湿った空気や、フェーン現象/フェーン風による異常な高温など、局地的に気象条件が厳しくなることがあります。
9月の発表例と過去データから学ぶこと
発表例
- 環境省のウェブサイト「熱中症警戒アラート等 発表状況と発表履歴」を見てみると、9月18日にも「熱中症警戒アラート」が発表されている地域があります。 WBGT公式サイト
- その他、9月中旬~下旬で日最高WBGTが33を超える予測が出た例が複数あり、発表対象となっています。これらは残暑+湿度などの条件が重なったケースです。
過去データ
- 救急搬送者数などの実績をみると、9月でも熱中症による搬送数は決して少なくない。たとえば、ある年の9月には熱中症による救急搬送者が2,000人を超える日もあり、5月~9月の期間全体の中でも一定割合を占めることがあります。 teramoto.co.jp
- 発表回数の統計でも、7~8月が多いとはいえ、9月に入ってからも警戒アラートがゼロではないことが制度開始から継続して確認されています。 気象庁+1
注意すべき点と対策
アラートが出ていなくても油断しないこと
アラートはあくまで発表の基準を満たす予測がなされたときに出されるものです。たとえ発表されていなくても、暑さ・湿度・日射条件が厳しい日はリスクがあります。特に下記のような状況では注意が必要です:
- 屋外での活動(作業・スポーツなど)
- 日差しが強い時間帯(正午前後~午後)
- 日陰・屋内でも風通しが悪い・夜間の気温が高い場所
- 高齢者・乳幼児・持病のある人など、熱中症の影響を受けやすい人
対策例
- 定期的な水分補給(こまめに・のどが渇く前に)
- 塩分補給も併せて(食事やスポーツドリンクなど)
- 適切な休息、屋内外の環境調整(風通し・日よけ・遮熱)
- 服装を見直す(通気性の良いもの、色の淡いものなど)
- 寝苦しさ対策:夜間の冷房や扇風機使用・窓の開け閉め・除湿などの工夫
情報の活用
- 気象庁・環境省のサイトで暑さ指数予測をチェックする。アプリ・メール配信サービスなども活用可能。 WBGT公式サイト+1
- 地域の自治体や学校・職場などで予防対策の呼びかけ・管理体制を整える。イベント等の計画時には天候予報を考慮する。
結論:9月だからと甘く見るな
「夏が終わった」という感覚があっても、9月には残暑・湿度・夜間の暑さなどが重なり、熱中症のリスクは依然として高いままです。制度としても、熱中症警戒アラートの発表対象期間は10月第4水曜日まで設定されており、気温が下がらない限り“警戒期”は続きます。暑さ指数(WBGT)が33を超える予測が出た日は、たとえ曇りがちでも、しっかりと予防行動をとることが、自分自身と周囲の人の健康を守る鍵です。