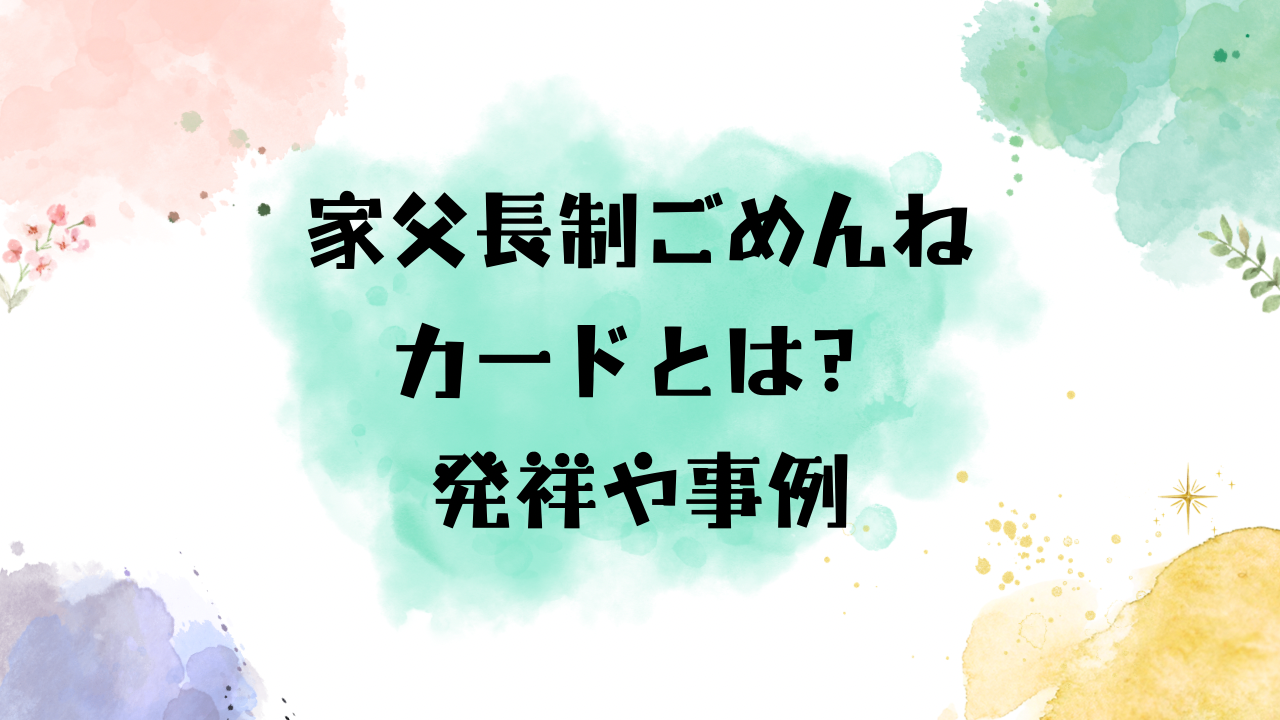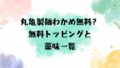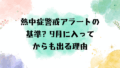「男の自分より“目下”である妻に叱られたので、それに免じて許してほしい」――そんな構図の謝罪コメントが、SNS上で“家父長制ごめんねカード”と揶揄され話題になっている。ことの発端は、2025年5月18日、自民党の江藤拓農林水産大臣が「私はコメを買ったことがない。支援者がたくさんくれるので売るほどある」と発言したことにある。米価高騰に直面する農家や消費者を前にした不適切な発言として批判が集まる中、翌19日、江藤大臣は「妻に怒られた」とコメント。これに対してネット上では「家父長制ごめんねカードを切った」と冷ややかな声が広がった。本記事では、この“家父長制ごめんねカード”という表現の意味、発祥、そして過去の類似事例について考察していく。
⸻
家父長制ごめんねカードとは何か?
“家父長制ごめんねカード”とは、男性政治家や有名人が不適切な発言や行動をした際に、「妻に叱られた」「家族に注意された」と発言し、それをもって「反省した」「間違いを認めた」とするコミュニケーション手法を揶揄する言葉である。
この表現は、表面上は「家族との関係性を大切にしている」姿勢をアピールしているように見えるが、実際には以下のような構図が問題視されている。
• 「妻に怒られた」という語りで、自分の発言を“つい口が滑った程度”に矮小化する
• 「自分はもともと悪意がなかったが、女性(=妻)に叱られて改めた」とすることで、責任の所在をあいまいにする
• 謝罪の本筋を個人の家庭内関係にすり替え、社会的な説明責任を果たしていない
こうした態度は、無意識のうちに“男性が主で女性は従”という家父長制的な価値観に依拠しており、なおかつ批判を避ける“逃げ道”として妻の存在を利用している点が問題とされる。
⸻
江藤農相の発言にみる典型例
江藤農水相の発言は、この「家父長制ごめんねカード」の典型といえる。5月18日、佐賀市で行われた自民党佐賀県連の政治資金パーティー「政経セミナー」において、米価高騰について問われた際、江藤氏は次のように語った。
「私はコメを買ったことはありません。支援者の方がたくさんくださるので、まさに売るほどある。」
米価高騰に苦しむ農家や消費者がいる中で、「売るほどある」という発言は感覚がズレていると受け取られ、SNSを中心に批判が殺到。すると翌日、江藤氏は記者団の前でこのようにコメントした。
「さっき妻から電話があってですね、怒られました。売るほどあるっていったのは言いすぎでした。売るほどは『ない』というのが妻からの話でした。」
これに対しX(旧Twitter)では、「家父長制ごめんねカードを切った」という投稿が拡散され、さらに炎上する事態となった。
⸻
“妻に怒られた”謝罪の歴史と発祥
この“妻に怒られた”形式の謝罪は、実は決して新しいものではない。政治家や著名人が不祥事後に「妻にこっぴどく叱られた」「家族に迷惑をかけた」と述べるのは日本のメディアでも繰り返されてきた構図である。
例を挙げれば、
• 不倫報道を受けた男性芸能人が「妻と子どもに土下座した」と述べる
• 差別発言を批判された政治家が「妻に注意されて初めて自覚した」と語る
• セクハラ問題で謝罪する際に「妻に恥ずかしくて顔向けできない」と述べる
いずれも、社会的責任というより“家庭内の懲罰”で十分とするような語りで、問題の本質をすり替えてしまう。
ネット上で「家父長制ごめんねカード」という用語が明確に使われ始めたのは、2020年代後半からと見られており、X(旧Twitter)やnoteなどで言説が共有される中で浸透したものと考えられる。
⸻
なぜ“カード”と呼ばれるのか?
“カード”という言い方には、ある種の“常套句”や“使えば一発逆転の免罪符”的な皮肉が込められている。いわば「ジョーカー(最強の切り札)」的な存在として、このカードを切れば一時的に批判が和らぐと考えている風潮を批判しているのだ。
とりわけ日本社会においては、家庭円満や“いい夫”像が評価されがちであり、「妻に怒られた」「妻を尊重している」というフレーズは、本人の人格を“柔らかく”演出する効果を持つ。その分、社会的な問題や構造的な課題をうやむやにする可能性も高い。
⸻
類似の“ごめんねカード”事例
以下はいくつかの典型的な「家父長制ごめんねカード」に類する事例である。
■ 某男性議員の「女房が一番怒ってた」発言
差別的な発言をした際、本人が「女房が一番怒っていた。『あんたバカじゃないの』と」と語り、謝罪としたもの。
■ 芸能人の不倫謝罪会見での「妻に全て話しました」コメント
公的な場での謝罪にもかかわらず、「妻に怒られた」「妻と子に許してもらえるよう努力する」と繰り返し、問題を家庭内の話に収めようとした事例。
■ SNS炎上時の「家族が一番つらい思いをした」型
差別・偏見に基づく発言に対し、「家族に申し訳ない」「子どもが学校で肩身の狭い思いをしている」と述べ、共感を得ようとする。
いずれも、本人の認識や社会的責任については曖昧なまま、「家族」が“盾”のように使われるパターンである。
⸻
“家父長制”という構造が見え隠れする理由
この“ごめんねカード”の根底には、「家庭の中で最終責任を負うのは夫(=家父長)であり、妻の忠告で軌道修正する」という昭和的な家族観が存在する。近年は男女平等やジェンダー意識が高まっているとはいえ、政治家やメディアの言説にはこうした“古い価値観”が根強く残っていることを浮き彫りにする。
⸻
本当の謝罪とは何か? 社会に問われる説明責任
“妻に怒られた”ではなく、なぜその発言が問題だったのかを、自分の言葉で説明し、社会に対してどう責任を果たすのかを語ることが本当の謝罪のあり方だ。
江藤農相のケースであれば、
• 支援者から無償で米を受け取る構造が、農業政策の公平性と矛盾しないのか
• 政府としてどう米価高騰に取り組むのか
• 「売るほどある」発言が、国民や農家にどう響いたのか自覚があるのか
といった点に答える必要がある。そうした説明なく、「妻に怒られたから訂正した」とする姿勢では、再発防止にも責任ある立場としての信頼にも繋がらない。
⸻
おわりに
「家父長制ごめんねカード」は、いわば“家庭内の恥ずかしさ”を前面に出すことで、社会的な責任の軽減を図るコミュニケーション手法である。しかしそれは、個人の問題を構造の問題にすり替えるトリックでもある。
この手の“カード”が使われ続ける限り、日本の公人による謝罪は、誠実な社会的説明からは程遠いままなのかもしれない。江藤農相の発言を契機に、私たち自身もまた、謝罪の言葉にどんな“構造”が隠されているのかを読み取る力が求められている。