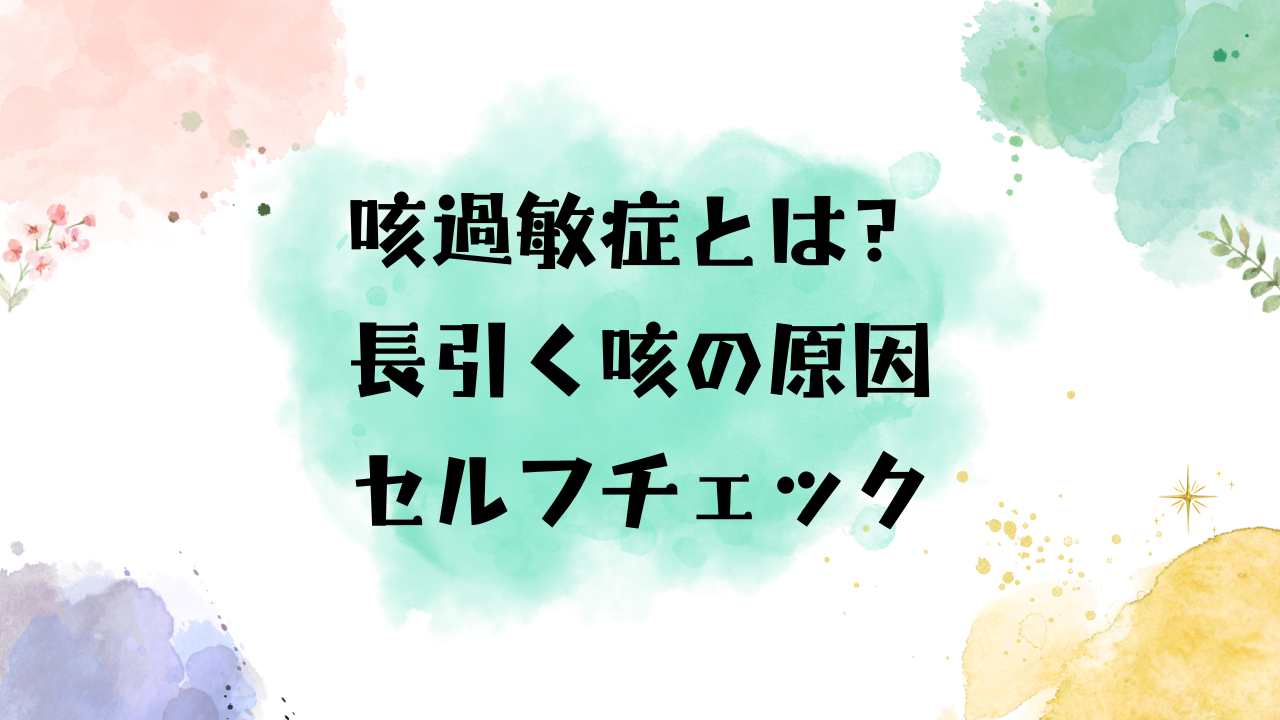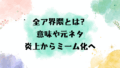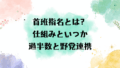エアコンの直風、柔軟剤の香り、たばこの煙、さらには会話や笑い声といった、日常でよくあるささいな刺激。これらによって急に咳き込み、止まらなくなってしまう――そんな症状に悩まされる人が増えています。その原因のひとつとして注目されているのが「咳過敏症」です。
従来は「体質」や「原因不明」と片づけられてきましたが、近年の研究によりその病態が明らかになり、診療ガイドラインにも加わるなど、治療への道筋が見え始めています。本記事では、咳過敏症の特徴や生活への影響、診断と治療法、そして日常生活でできる対策について詳しく紹介します。
咳は体を守る大切な防御反応
咳は本来、体に侵入したウイルスや細菌、ホコリなどの異物を体外に排出するための大切な防御反応です。
風邪やインフルエンザなどの感染症をきっかけに始まることが多く、通常であれば数週間で治まります。しかし、8週間以上続く「慢性咳嗽(まんせいがいそう)」に移行するケースもあります。日本全国で約300万人が慢性咳嗽に悩んでいると推定されており、決して珍しい症状ではありません。
特徴的なのは「四六時中咳が出るわけではなく、特定のきっかけで強く咳き込む」ことです。滋賀県長浜市での大規模住民調査では、慢性咳嗽の悪化要因として「夜間・早朝」「花粉シーズン」「天候の変化」などが挙げられました。
さらに、たばこの煙や香水の香り、冷気、湿気、運動などが引き金になることも多いと報告されています。
生活を大きく乱す“長引く咳”
慢性咳嗽は生活の質(QOL)に大きな影響を与えます。
- 夜間に咳が強くなり睡眠が妨げられる
- 集中力が落ち、仕事や家事の効率が低下する
- 公共交通機関や会議中に咳き込み、周囲の視線が気になる
- 外出や人前での発言を控えるようになる
海外のデータでは、慢性咳嗽患者の仕事のパフォーマンスが平均3割低下していたとの報告もあります。
さらに、咳によって肋骨を骨折する、強い咳込みで失神する、女性の場合は尿もれが起こるなど、身体的なトラブルに発展するケースもあります。
「咳が長引くと、身体的負担だけでなく心の健康や社会生活にも深刻な影響が及びます」と警鐘を鳴らしています。
その咳、もしかしたら「咳過敏症」?
慢性咳嗽の新しい概念として注目されているのが「咳過敏症症候群(CHS)」、通称「咳過敏症」です。
咳過敏症の特徴は、以下のように日常的で軽微な刺激で咳が誘発されることです。
- エアコンの直風
- 柔軟剤や香水のにおい
- たばこの煙
- 会話や笑い声
また、咳をしていないときでも「のどのイガイガ感」「咳の衝動が常にある」と訴える患者が多く、いわゆる“隠れ慢性咳嗽”と呼ばれることもあります。
セルフチェックの目安
以下の項目のいずれかに当てはまる場合、咳過敏症の可能性があります。
- 8週間以上咳が続いている
- 特定のにおいや冷気で咳が出る
- 咳のせいで睡眠や仕事に支障がある
- 咳止め薬が効かない
- 咳が出そうな不快感や衝動を常に感じる
これらに複数当てはまる場合は、呼吸器内科での受診を検討した方がよいでしょう。
咳過敏症の原因 ― 神経の“過敏化”
では、なぜごくわずかな刺激で咳が出やすくなるのでしょうか。
咳過敏症は「気道の知覚神経が過敏になっている状態」だといいます。
- 気道表面にある刺激を感知する神経が通常より多い
- 神経の枝分かれが多く、感度が高い
- 脳幹で咳を抑制する回路が弱くなっている
つまり、末梢から脳までの「咳の神経ネットワーク全体」が過敏化しており、わずかな刺激で咳反射が起きてしまうのです。
医療機関を受診するときのポイント
長引く咳で受診する場合、基本は呼吸器内科が適しています。鼻やのどの症状が強い場合は耳鼻咽喉科でもよいでしょう。
診察を受ける際には、以下の情報をメモして伝えると診断がスムーズになります。
- 咳が続いている期間
- 咳が出やすい状況(冷気・柔軟剤など)
- これまでに使用した薬とその効果
「柔軟剤のにおいで咳が止まらなくなる」など、きっかけとなる体験は診断に役立つため、詳細を記録しておくことが重要です。
咳過敏症に有効な新薬も登場
診断ではまず肺がんや結核、間質性肺炎などの重大な疾患を除外します。その後、アレルギー性鼻炎、咳ぜん息、胃食道逆流症、新型コロナ後遺症などが原因かどうかを確認します。
それでも改善が見られない場合や原因不明の場合に、咳過敏症と診断されることがあります。
治療には2021年に承認された P2X3受容体拮抗薬 が用いられることがあります。この薬は気道の神経の過敏な反応を抑え、咳反射を鎮める効果が期待されています。
咳を減らすための日常生活の工夫
医療機関での治療と並行して、日常生活での工夫も大切です。
胃食道逆流症を避ける生活習慣
- 食後すぐに横にならない
- 早食い・大食いを避ける
- コーヒー、チョコレート、脂っこい料理や香辛料を控える
のどを守る習慣
- マスクで乾燥を防ぐ
- こまめに水分をとる
- うがいを習慣化する
咳が出そうになったときの対処法
- 顎を引き、胸に近づける姿勢で水分を飲む
- 両手を胸の前で合わせ、息をこらえて飲み込む
- 氷や飴をなめる、ガムをかむ
- 口をすぼめて呼吸する
こうした方法で、咳の衝動を抑えたり、咳の回数を減らしたりすることができます。
まとめ
咳過敏症は、日常のささいな刺激で咳が止まらなくなる新しい病態です。これまで原因不明とされてきた「長引く咳」に対して診断や治療法が整いつつあり、生活の質を大きく改善できる可能性が出てきました。
「たかが咳」と軽視されがちですが、仕事や人間関係に大きな支障をきたすことも少なくありません。長引く咳に悩まされている人は、ぜひ呼吸器内科を受診し、自分の症状をしっかり医師に伝えることが大切です。
咳過敏症を正しく理解し、生活の工夫や治療を取り入れることで、快適な日常を取り戻すことができるでしょう。