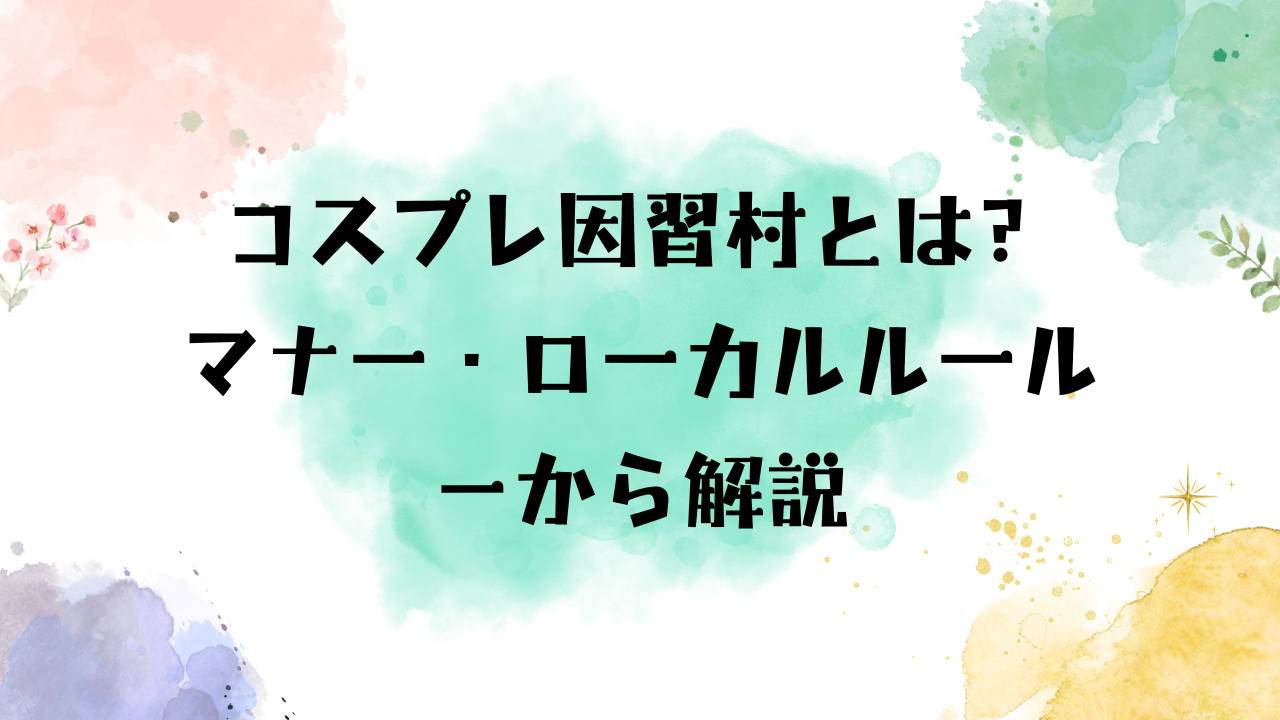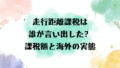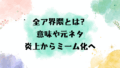近年、SNSを中心に「コスプレ因習村」という言葉を耳にする機会が増えています。これは、コスプレジャンルに存在する独特のマナーやローカルルール、そしてそれを守らない人に対する厳しい批判・排斥の空気を揶揄したネットスラングです。とりわけ2025年4月、大阪・関西万博でのコスプレをめぐる議論を契機に広く使われるようになり、コスプレ界隈を象徴する言葉の一つとして急速に浸透しました。本記事では、この「コスプレ因習村」という言葉の意味や背景、マナーの成り立ち、批判と擁護の両面から一から詳しく解説します。
「コスプレ因習村」とは何か
「コスプレ因習村」とは、コスプレ界隈に存在する暗黙のルールやマナーを過度に重視し、それに違反する人物を厳しく批判する閉鎖的な空気を指す言葉です。
もともと「因習村」とは、現代的な価値観から見れば時代遅れ・不合理とされる慣習を固守し、共同体の内部規範に従わない者を排斥する小さな共同体を揶揄する表現です。これをコスプレ文化に当てはめて使ったのが「コスプレ因習村」という言葉なのです。
特にSNS上では、マナーをめぐる批判合戦や炎上がたびたび発生しており、外部の人からは理解しがたい「閉鎖性」が強調されることも少なくありません。
きっかけは大阪・関西万博でのコスプレ論争
「コスプレ因習村」という言葉が広まる契機となったのは、2025年4月に大阪・関西万博で起きた一件でした。
あるコスプレイヤーが、会場内で特定作品のコスプレと撮影を行ったところ、界隈から「スタジオやコスプレイベント以外でのコスプレは控えるべき」という批判が相次ぎました。
しかし、この行為自体は会場の公式ルールで明確に禁止されていたわけではありませんでした。そこで支持者の一部が「ルールで禁止されていないのに叩かれるのはおかしい。コスプレ界隈は規則ではないマナーを押し付けている。まるで因習村だ」と反論し、以後この言葉が拡散していったのです。
当のコスプレイヤー本人も後にこの言葉を用いて批判に対抗し、ネット上で議論がさらに広がりました。
コスプレ文化とマナーの特殊性
コスプレ因習村と呼ばれる背景には、コスプレ文化の特殊性があります。
法的にグレーな二次創作活動
コスプレの多くは既存作品のキャラクターを題材にした「版権コスプレ」です。これは著作権の観点から見るとグレーゾーンであり、作品や権利者に配慮した行動が求められます。
コスプレイヤー本人が「作品」となる
漫画や小説などの二次創作と異なり、コスプレでは評価の対象がコスプレイヤー本人となります。そのため、衣装の完成度だけでなく素行や立ち居振る舞いが悪目立ちしやすいのです。
人数が少ないため監視が強まりやすい
コスプレイヤー人口はオタク全体から見れば多くなく、界隈が狭いため相互監視や牽制が強まりやすい傾向があります。その結果、他ジャンルに比べて「ルールやマナー」を重視する文化が発展しました。
具体的なマナー・ローカルルールの例
コスプレ因習村と呼ばれる背景には、多くの「暗黙のルール」が存在します。代表的なものを紹介します。
- スタジオやイベント以外でのコスプレ禁止
公共の場での無許可コスプレは、盗撮や映り込みによるトラブル、条例違反のリスクがあるため忌避されがち。 - 過度な露出・武器の持ち歩き禁止
公序良俗や法律に触れる可能性があり、一般市民の目もあるため特に警戒される。 - 撮影時のエチケット
無断撮影の禁止、SNS掲載時の加工や表記ルール、相手への事前確認など。 - SNSでのふるまい
炎上を避けるため、作品や他レイヤーへの批判は控える、相互のトラブルは内々で解決するなどの暗黙の了解。
これらは一部は合理的ですが、一部は形骸化して「なぜ守る必要があるのかが不明確」になっているため、新規参入者には因習のように映るのです。
晒し・監視文化と閉鎖性
コスプレ因習村と呼ばれる理由の一つに、界隈特有の「晒し文化」があります。
問題行動を起こしたと見なされたコスプレイヤーやカメラマン(カメコ)のSNS投稿を監視し、掲示板やSNSで晒し上げる行為が少なくありません。注意喚起という名目ではありますが、実態は攻撃的なアンチ活動になることもあります。
このような「監視の目」は、界隈に強い警戒心を生み、結果的に外部から「閉鎖的で居心地が悪い」と見られる原因になっています。
マナーは本当に「因習」なのか?
一方で、すべてのマナーが無意味な「因習」というわけではありません。
例えば、スタジオ外でのコスプレが嫌われる背景には、盗撮対策や法律違反の防止、一般市民への迷惑防止といった正当な理由があります。衣装や小道具の持ち運びには銃刀法や軽犯罪法が関わるケースもあり、ルールは原作やコスプレイヤー自身を守る目的で受け継がれてきました。
問題は、その本質的な理由が共有されず、単なる「守るべき作法」として残ってしまう場合です。合理性を失ったルールが「因習」と呼ばれるのです。
原作へのリスペクトと一般の方への配慮
「コスプレ因習村」と揶揄されるマナーやローカルルールの多くは、決して無意味なものではありません。むしろ、その背景には原作作品へのリスペクトと、一般市民や施設利用者への配慮があります。
コスプレは原作があって初めて成り立つ文化であり、原作への敬意を欠いた行為は、権利者からの不信感やトラブルを招きかねません。無断で商業利用したり、作品を貶めるような撮影・発言は、界隈全体への悪影響につながります。
また、コスプレイベント以外の場所では、一般の来場者や通行人が予期せずコスプレに遭遇することがあります。その際に不快感や不安を与えないように、露出や武器の持ち歩き、撮影マナーなどのルールが作られてきました。これらは「オタクの内輪ルール」ではなく、社会との摩擦を避け、趣味活動を続けやすくするための工夫とも言えます。
つまり、「因習」と呼ばれるものの本質は、原作とコスプレイヤーを守り、一般社会との共存を図るための知恵なのです。ルールを因習と切り捨てるのではなく、その背景にある目的を理解することが重要だと言えるでしょう。
「因習村」と呼ばれる側の認識
SNS上で「コスプレ因習村」と発言している人の中には、もともとコスプレイヤーでもカメラマンでもない層も少なくありません。
彼らは複雑な背景を知らないため、合理的なマナーすら「意味不明な因習」と感じてしまうことがあります。また、批判を受けた当事者が「嫉妬で叩かれているだけだ」と受け取り、都合の悪いルールを「因習」と呼んでしまうケースもあります。
つまり、「コスプレ因習村」という言葉は、立場や知識の差によって見え方が大きく異なるのです。
因習批判と健全なマナー維持のバランス
コスプレ文化を健全に保つには、明文化された施設・イベントのルールを最優先としつつ、一般市民や関係者に迷惑をかけない最低限のマナーは必要です。
しかし、時代に合わないルールや合理性を失ったルールは見直す必要があります。重要なのは、「何のためのルールか」を共有することです。
合理的なマナーは界隈の信頼を守りますが、不合理な因習は新規参入者を遠ざけ、文化全体を停滞させかねません。
まとめ
「コスプレ因習村」とは、コスプレ界隈におけるマナーやローカルルールが、閉鎖的で因習的に見える状況を揶揄したネットスラングです。
確かに界隈には独特の監視文化やローカルルールが存在しますが、その多くは著作権や法律遵守、一般市民への配慮といった合理的な目的から生まれたものです。
問題は、その意義が伝わらず形骸化し、外部から「不合理な因習」と見なされてしまうことにあります。今後コスプレ文化が健全に発展するためには、マナーの本質を共有し、時代に即した柔軟な見直しを行うことが欠かせません。