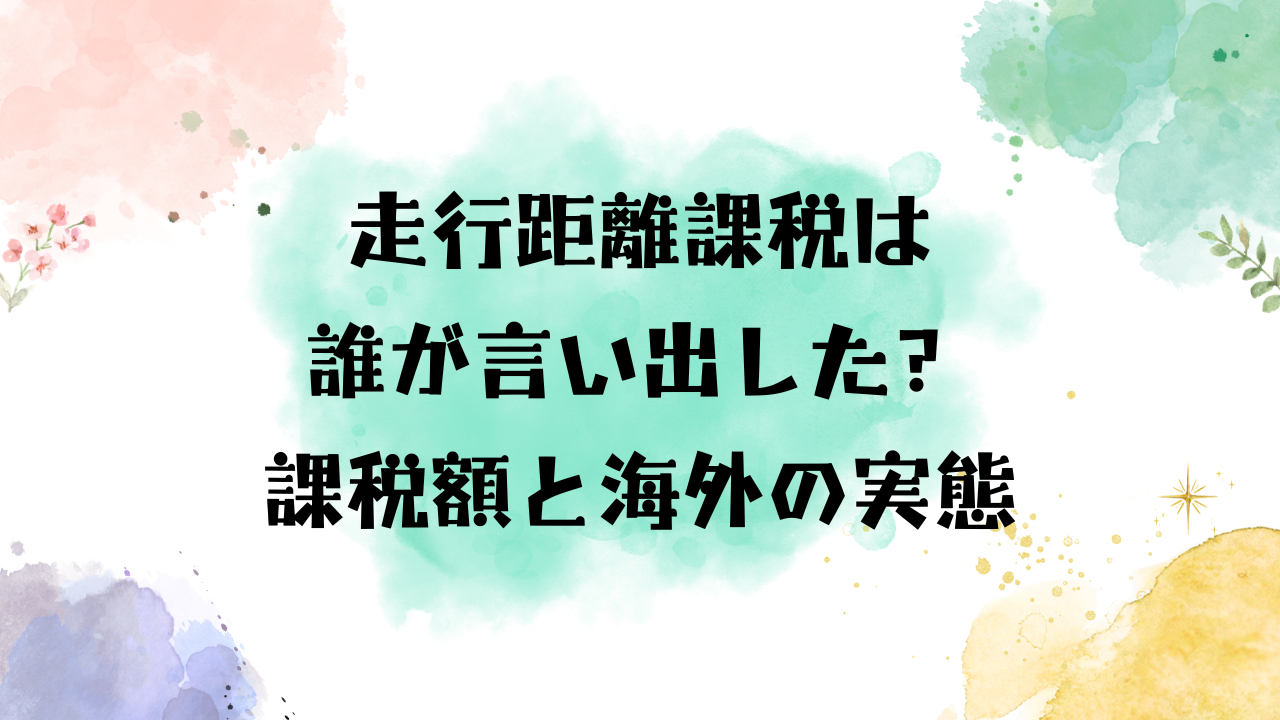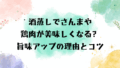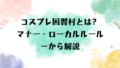「走行距離課税」(あるいは「走行税」「マイレージ課税」「Road-Usage Charge」等)は、車両が実際に走行した距離に応じて税負担を決める税制度のことを指します。これまでの自動車税制度では、排気量や車両重量、燃料消費量、燃料税、所有期間などが主な課税指標でしたが、電気自動車(EV)をはじめとする“燃料消費に依存しない、あるいは消費が極めて少ない”“燃費が良い”車両の普及が進む中で、従来型の税収構造に変化が生じています。特にガソリン税や軽油税が道路整備や維持管理の主な財源であった場合、燃料を使わない車両にはこの税収が見込めず、将来的な道路インフラの財源不足を懸念する議論が出てきました。そのような流れで、「走行距離課税」は日本でも議論の俎上に上がるようになっています。
本稿では、まず「誰が」「いつ」「なぜ」この制度を提案・言及し始めたかを整理し、その後バイクやガソリン車等既存車両への影響、具体的な課税額の想定例、さらには海外での導入・検討事例を比較し、メリット・デメリットを含めて実態を明らかにします。
小見出し
- 日本における走行距離課税の発端と提起者
- 主な検討内容と現在の議論状況
- バイク・ガソリン車にどのような影響があるか
- 海外における走行距離課税の実態(導入国・制度概要)
- 課税額の具体例と比較(国内外)
- メリット・デメリット、制度設計上の課題
- 将来の見通しと政策的含意
本文
1. 日本における走行距離課税の発端と提起者
- 鈴木俊一財務大臣(当時)による言及(2022年10月20日)
走行距離課税が「一つの考え方」である、との発言が初めて大きく注目を浴びたのは、2022年10月20日の参議院予算委員会でのことです。鈴木財務相は、電気自動車(EV)はガソリン車と異なり、走行段階で燃料課税(ガソリン税や軽油税など)を支払っていない点、および車重が重いため道路補修への負荷が大きい可能性を指摘し、いずれ時期を見て「負担のあり方を考えていく必要がある」と述べ、与党の税制改正議論も踏まえて対応を検討したいという意向を示しました。 Reuters Japan+2JBpress(日本ビジネスプレス)+2 - 政府税制調査会での審議
鈴木財務相の言及後、同年10月末には政府税制調査会(与党・学識者などによる税制見直し・提言を行う場)でも、走行距離に応じた課税制度の可能性が議論されました。制度の導入・対象範囲、既存の燃料税やガソリン税・自動車税等との関係、二重課税などの課題が整理されていますが、まだ方針決定には至っていません。 Pai-R+2JBpress(日本ビジネスプレス)+2 - なぜ今、議論されはじめたか
主な背景には次のような要因があります。- EV・ハイブリッド車の普及:燃料を使わないまたは少ない車両が増加すると、燃料税収が減少する。
- 燃費改善による燃料使用量減少:内燃機関でも燃費が良くなっており、ガソリン使用量での課税だけでは道路使用量や損耗を公平に反映できにくくなる。
- 道路維持・補修等のインフラコストの増加:道路の老朽化、補修需要の増加、および気候変動・自然災害等によるインフラ被害増加など。これらを賄う安定財源の確保。
- ガソリン税の暫定税率問題:日本ではガソリン税・地方揮発油税に暫定税率という仕組みがあり、「本来の税率」の上に上乗せされている部分が現在も継続されている。これが将来的に見直される可能性があり、その代替案として走行距離課税が候補になるとの見方があります。 カーバイバイ+3自動車情報誌「ベストカー」+3JAF交通安全トレーニング+3
2. 主な検討内容と現在の議論状況
- 対象車両
EVやプラグインハイブリッド車(PHEV)、ハイブリッドなど燃料消費が少ない車両が中心的に議論されており、これらに対して燃料税だけでは税負担が少ないとの見方があります。ガソリン車については、現在のところ「走行距離課税」の対象とするかどうか、どの程度併用するか、あるいは燃料税をどう調整するかが焦点です。バイクについても話題には上がりますが、自動車に比べて道路への負荷(重量・損耗)や利用頻度が異なるという点で特別扱いの検討が必要とされています。 カーバイバイ+2JAF交通安全トレーニング+2 - 測定方法・制度設計の論点
走行距離をどのように正確に測定するか(オドメーター、GPS、自己申告など)、プライバシー保護、地方在住者や運輸業・物流業の費用負担、公平性(都市/地方、頻繁使用者/非頻繁使用者など)、既存の自動車税・燃料税や重量税等との二重課税の懸念などが挙げられています。 MOTA(旧オートックワン)+2東京都税務署+2 - 導入時期・見通し
現時点で正式な法案や施行日程は確定しておらず、制度の具体的内容も流動的です。憶測では2030年あたりを見越す意見がある一方で、「もう少し先になる」「部分的・限定的な適用から始まる」という見方もあります。 MOTA(旧オートックワン)+1
3. バイク・ガソリン車にどのような影響があるか
- ガソリン車
現行ではガソリン車は燃料を使うたびに燃料税・揮発油税等を支払っており、ガソリン税収こそが道路整備・維持管理の主な財源の一部となってきました。走行距離課税が導入される場合、ガソリン車にも追加課税が発生する可能性がありますが、「燃料税との重複」(既に燃料税を支払っている走行距離にも課税されること)になるとの指摘があります。もし燃料税を一定額減らしつつ、走行距離課税を併用する形にすれば二重課税の問題を緩和できますが、制度設計次第で負担が大きく変わります。 MOTA(旧オートックワン)+1 - バイク(オートバイ)
バイクは車体やタイヤの重量が軽く、道路への直接的な損耗(舗装の圧力・摩耗など)の負荷は四輪車より小さいと考えられます。そのため、もし走行距離課税を導入する場合、バイクをガソリン四輪と同列に課税対象とするか、別の基準を設けるかが問題になります。現時点の日本の議論や報道で、バイクだけを特別に除外する/軽減するという具体的な税額設定案は出てきていません。 カーバイバイ+1 - 影響の方向性
“走る距離が長い車両・頻繁に使用する用途”(通勤、営業、配送、長距離移動など)では負担が増える可能性。逆に、あまり走らない車や利用が限定的な車両ではトータルの税負担が軽くなる場合もあり得ます。バイクについては、普段使いの距離が四輪車より短いケースが多いため、制度によっては“恩恵を受ける”可能性がありますが、燃料税と併用されたり、利用頻度が高い場合には負担増になることも。
4. 海外における走行距離課税の実態(導入国・制度概要)
以下、主な国・地域での制度とその特徴を整理。
| 国/地域 | 制度名等 | 対象・範囲 | 課税単価・重量別率など | 特徴・補足 |
|---|---|---|---|---|
| ニュージーランド | Road User Charges(RUC)制度 JAF交通安全トレーニング+2ウィキペディア+2 | 軽油車(ディーゼル車)や大型車、3,500 kg 超などの“燃料が源泉で課税されない車両”が主対象。普通のガソリン車は通常燃料税が源泉でかかるので、RUCの対象外となることが多い。 ウィキペディア+2nzta.govt.nz+2 | 車両重量や軸数などに応じて、1000kmあたりのライセンス費用が異なる。例:2軸車両3500kg以下ならNZ$76/1000km(=約0.076NZ$/km)など。重量が大きい車はより高率。 nzta.govt.nz | かなり歴史のある制度で、制度設計も成熟。道路使用に応じて課金する公平性、重量・損耗を反映する仕組みが含まれる。 |
| アメリカ合衆国(オレゴン州など) | “RUC”または“VMT”(Vehicle Miles Traveled)等の制度実験・導入例 全米州議会会議+1 | 主に燃費が良い車両・EVの普及に対応するための代替・補完制度として導入/実験。四輪乗用車も含まれることがある。 カーバイバイ+1 | オレゴン州では1マイルあたり1.8セント(USD)といった率が例示されており、燃料税削減分の補填や補正を行う仕組みあり。 全米州議会会議 | 州ごとに制度がバラバラで、利用者の選択性を残すタイプも。GPS等技術や自己申告などでの距離測定、プライバシー問題なども議論されている。 |
| 欧州各国(ドイツ、フランス等) | 特に大型トラック等、重量車を対象とした道路使用料・距離課税制度あり/検討あり。 カーナリズム+1 | 主に商用車・貨物車など多数の軸・重量がある車が対象。乗用車への全面適用は未だ限定的/議論中。 | 課税率は国によって大きく異なる。貨物車等は軸数・総重量・通行距離・時間帯など複数要素を組み合わせるものが多い。 | 制度導入にあたっての反対運動が強いこともしばしば。道路政策・交通政策・環境政策と絡む。 |
| その他地域 | カナダの一部州、オーストラリア、一部アジア諸国でも研究/試験的導入が検討されている。 JAF交通安全トレーニング+1 | 対象・範囲・頻度は国によってさまざま。 | 単価・徴収方法がロードユーザーの利用や負担能力等を加味して設計される。 | 公聴会・社会的合意形成が制度の成否を左右する要因となっている。 |
5. 課税額の具体例と比較(国内外)
制度が正式に定められていない日本では、確定した「バイク・ガソリン車に対する走行距離課税額」は公表されていません。ただし、海外の例・制度設計から「日本で仮に導入されたらこれくらいになるか」という試算がされているものや、海外制度での具体数値があります。
| 国・地域 | 車両タイプ/重量・仕様 | 課税単価例/1000kmあたり | 試算・備考 |
|---|---|---|---|
| ニュージーランド | 2軸、3500kg 以下の“Powered vehicles” | NZ$76/1000km(=約0.076NZ$/km) nzta.govt.nz | これは重量区分が軽めの乗用車クラス。重量の大きな車両は1,000kmあたりもっと高くなる。 |
| オレゴン州(米国) | 任意登録の乗用車等 | 約 1.8セント USD/マイル(1マイル=約1.6km → 約0.011‐0.012 USD/km) 全米州議会会議 | 燃料税と併用されており、燃費の良い車/EVには補正・割引が設けられていることが多い。 |
| 日本(仮想試算) | ガソリン車・EV混在の乗用車 + 1万km/年程度走行のケースなどを想定 | メディア上で「1kmあたり2円」などという仮定が紹介されることがある。たとえば、「走行距離税は1 km あたり2円なら、年間1万 km で 2 万円」といったシミュレーション。 note(ノート)+1 | ただし、この種の試算は単純モデルで、重量・車種・道路損耗度合い・燃料税の取り扱いなどを考慮していないことが多い。実際の税額はこれらをもとに大きく上下する。 |
また、ニュージーランドでは EV/プラグインハイブリッド車でも、重量区分に応じて走行距離課税(RUC)をかける区分が設けられている例があり、ガソリン車と完全に同じ構造ではないが、かなり近づけた公平性を意識した設計がなされている。 nzta.govt.nz
6. メリット・デメリット、制度設計上の課題
メリット
- 公平性の向上:走った距離に応じて課税されるため、道路を頻繁に利用する人がより多く負担し、あまり使わない人や近距離使用中心の人は負担が軽くなる可能性。
- 燃料税収の代替・補完:EVや燃費の良い車が増える中で、燃料税収が将来的に減少することが予想される。これを補う仕組みとして有効。
- 交通政策・環境政策と整合:無駄な走行抑制、燃費改善・環境負荷の低減など政策目的に寄与できる。
- 道路維持・損耗の実態反映:特に重量車や多軸車の損耗が道路に与える影響を距離と重量等で反映させることで、使用者負担(受益者負担)の原則を強化できる。
デメリット・課題
- 二重課税の懸念:ガソリン車についてはすでに燃料税を払っているため、「燃料税+走行距離課税」となると負担が過重になる可能性がある。制度設計でどちらかを調整する必要あり。
- 測定・管理コスト:走行距離を正確に測るシステム(GPS・オドメーター管理・報告制度など)の整備が必要。メンテナンス、改ざんや不正測定のリスク、データ管理・プライバシー保護の問題。
- 地方・長距離ドライバーへの負担増:公共交通が少なく車依存度が高い地域では、毎年の走行が必然的に多いため、負担が相対的に大きくなる。生活条件の格差を生む恐れあり。
- 物流・運送業への影響:貨物車や配送トラック、大型車が多い業界ではコスト増が避けられず、最終的に物価に転嫁される可能性。
- 制度移行時の調整問題:既存税制度との関係(例えば自動車税・重量税・燃料税など)、過去の購入車両・バイク等の特例、経過措置などをどう設定するか。
7. 将来の見通しと政策的含意
- 今後の導入可能性
日本では、制度の中長期的な税制改革の枠組みの中で、2020年代後半から2030年代前半にかけて何らかの走行距離課税が導入される可能性が指摘されています。ただし、全面導入よりは限定的・段階的な適用が現実的だとする見方が多いです。特定用途(商用車、物流車両、大型車等)または燃料を使用しない/使いにくい車種(EVなど)に対して優先導入する案等が可能性として議論されています。 MOTA(旧オートックワン)+2JAF交通安全トレーニング+2 - 政策設計のキーポイント
制度が納得されるためには、以下のような設計上の配慮が不可欠です:- 燃料税との整理:燃料税をどのように減税・廃止するか、あるいは距離課税と併用するか。
- 対象車種・重量・利用形態の区分:バイク・軽車両・乗用車・商用車などで負担能力や道路損耗度合いが異なるため、適切な区分が必要。
- 距離測定とプライバシー保護:GPS等を使う場合、データの収集・管理・匿名化などに関する制度設計と法制度。
- 地方と都市格差への配慮:交通代替手段の少ない地方で車を使わざるを得ない人の負担過多にならないような補助的措置など。
- 制度移行と経過措置:既存税制との調整、過去購入車の扱い、既存ユーザーの影響を緩和する仕組み。
- 社会的合意形成:ユーザー、業界、自治体、地域住民等の理解を得るための説明責任と交渉。
- 政策的含意
走行距離課税の導入は、単に税収確保の手段だけでなく、自動車やモビリティ全体のあり方を見直す契機にもなり得ます。交通インフラの使い方、公共交通整備、都市計画、自動運転やシェアリングカーなどの新しい移動手段への対応、環境政策(CO₂排出削減・低公害車促進)など、多くの政策分野と連動します。
結びに(まとめ)
走行距離課税は、内燃機関依存からの脱却・EV普及が進む中で、燃料税収の将来的な減少に対する財源確保と道路インフラ維持の観点から、国内外で真剣に考えられている制度です。日本では、2022年の鈴木財務相の「一つの考え方」という発言が発端となり、制度設計の議論が進んでいますが、バイクやガソリン車に関する具体的な課税額は未定であり、多くの政策的・技術的課題が残っています。
海外事例を見れば、ニュージーランドやアメリカの一部州では既に類似制度が機能しており、制度設計次第で公平性をかなり保つことが可能であることが示されています。一方で、負担増を感じる層もあり、地域差や利用形態の差をどう織り込むかが導入のカギとなるでしょう。